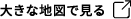名水を生み出す山林とその管理
「私は大学卒業後、材木問屋に就職したんです」と意外な第一声。「うちはいわゆる資産家というやつで、そうした家の長男の最も大事な仕事は資産管理なんです。小澤家の資産は200haの山林。山や木材のことをよく知っていないと先祖代々引き継がれたものを守ることはできませんから。」ということは林業と清酒業と両方を営んでいるのですかと問うと、「輸入木材に押され、林業を生業として成立させるのは難しいのが現状です。とはいえ山林は水の要。個人の資産であると同時に公共性を担っていますから、放っておくことはできません。」東京都の重要な水源・多摩川の水を育む山林を守るためには、収益を上げるために木を育てるという考え方から、環境を守るために木を育てるという方向に、意識を変えていかなければなりません。「昔とは異なる形ですが、多摩川の水質を管理し、100年後も維持できるようにするには、膨大な山林をどのように維持継続できるかということが課題。時代に合わせた新たな林業なんです。」豊かな山林が美しい水を育み、そしてその水こそがこの地で長い間、銘酒といわれる酒を造り続けられる所以なのでしょう。