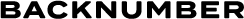東京都日野市、京王線高幡不動駅から歩いて20分、住宅街でありながら今も用水路の残るどこか懐かしい街並みを抜けると、コミュニティガーデン「せせらぎ農園」があります。
入り口でまず目に飛び込んでくるのは、大きな「生ごみボックス」。
ここの最大の特徴は、「生ごみは宝だ!燃やすなんてもったいない」という志ある市民が集まり、生ごみ堆肥を生かす場として誕生した農園でありコミュニティの拠点だということです。
活動のきっかけは2000年、市が実施した「ごみ改革」にさかのぼります。
多摩地区で不燃ごみ量ワースト1だった日野市は、二つのごみ減量策を始めました。
① ダストボックスを廃止し、原則戸別収集方式に変更 。
②ごみ袋の有料化( 有料指定袋制を導入し、中袋40円、大袋80円とあえて高く設定)。
この結果、ごみ量の半減を達成しましたが、さらなるごみ減量のために、可燃ごみの約40%を占める生ごみを何とかしたいと2002年に発足したのが、市民による「ひの・まちの生ごみを考える会」です。

広さ30アールの農園には、手作りの作業小屋と日よけのぶどう棚があり、夏季は涼みながらランチを楽しむ。
コミュニティガーデン発足のきっかけとなったのは、2004年にスタートした日野市の「一般家庭生ごみ収集堆肥化モデル実験」でした。
代表の佐藤美千代さんによると、当初は第八小学校・校区の有志22世帯の生ごみを、障害者の就労支援をする「NPO法人やまぼうし」が軽トラックで集めて八王子の鈴木牧場まで運び、牛糞と混ぜた堆肥にして販売する実験を、市のごみゼロ推進課と協働で行いました。
その後、鈴木牧場が閉鎖したため、地域内で堆肥を活用する場として、地主さんの協力を得て、2008年にオープンしたのが「せせらぎ農園」です。
「菌ちゃん農法」で知られる自然農法家・吉田俊道さんに指導を仰ぎ、生ごみを直接畑に投入し、米ぬかボカシで発酵促進させる方法で土づくりを始めました。
一番多い時では200世帯、年間30トンの生ごみを収集し、市民、地域、行政が一体となった活動をしてきました。
畑が区画整理予定地となった2023年度からは、車での生ごみ回収をやめて、登録利用者による持ち込み生ごみを堆肥場で完熟堆肥を作る方式に変更しました。



生ごみを落ち葉などと混ぜて積み上げ、定期的に攪拌して空気に触れさせると、約60℃~70℃の発酵熱が続き、約3カ月で完熟発酵堆肥になる。
生ごみリサイクル堆肥の仕組みは?
現在、生ごみを持ち込むのは、60世帯。各家庭が専用の抗酸化溶液配合が入ったバケツで生ごみを持参し、備え付けのボックスに投入します。その上には、落ち葉や竹チップ、竹炭など、備え付けてある有機物をかぶせるのがルールです。これは発酵を促進させるためです。
生ごみボックスが満杯になると、その隣にある堆肥場へ移します。定期的に攪拌して空気に触れさせると、約3カ月で完熟発酵堆肥に生まれ変わります。



農園メンバーには大まかな担当があり、それぞれが自分の持ち場をやりがいを持って耕す。畑の真ん中を流れる用水路は、道具の洗い場や遊び場にもなる。
コミュニティガーデンと農園の違いは!?
約30アールの広さの農園には、作業小屋、ピザ窯、育苗エリア、ハーブガーデン、花や野菜畑、市内の公園などから集めた落ち葉の堆肥場もあります。
畑の真ん中には用水が流れ、野菜や道具を洗ったり、子どもたちの遊び場になっています。近隣の保育園の散歩コースにもなっていて、年齢も様々な人たちが集まります。
訪ねたのは平日でしたが、20人近くがそれぞれの持ち場で作業をしているのが印象的でした。野菜の苗を植え付けている人、耕運機を扱う人、草取りや花の世話をする人、作業小屋の中ではお昼にみんなで食べる野草の天ぷらを揚げる人など、みんなが主役で自主性を持ち、役割を担っているのです。

20年以上、活動を牽引してきたコミュニティガーデンせせらぎ農園代表の佐藤美千代さん。
佐藤さんは、
「コミュニティガーデンの一番の目的は、いい野菜を作ることではないんです。いろんな人が集まってくるので、何かあるたびにみんなで話し合ってルールを決めます。一人に仕事が偏らないように、役割分担もあります。うまくいかないこともあるけど、6割できたら十分。一人一人が主体的に考えて、楽しく働ける場であることが大切だと思っています。」
と、話してくれました。

せせらぎ農園メンバーの皆さん。作業は、火、木、日曜 の週3回だがいつでも出入りは自由。
今では、近隣の保育園、小学校、中学校、大学等を含め、年間延べ4,000人以上が訪れ、生ごみリサイクルの情報発信基地として、また、環境問題や堆肥での野菜づくり、食育の講座を開くなど、教育、福祉、まちづくりの拠点になっています。
2020年には、一般社団法人TUKURUを設立し、新たに「東平山ハチドリ農園」や、地区センターの庭などで、第2第3のコミュニティガーデンが始まっています。

作業小屋にて、ニセアカシアの花や畑でとれた野草を天ぷらにして、みんなでランチづくり。
佐藤さんは、
「農地、公園、空き地、私有地に関わらず、まちのあちこちに、ゆるやかなみんなの居場所の“コモン(共有地)”を増やしたい。市民が楽しみながら、運営していく農園が増えれば、採れたて野菜のおいしさや、農家さんの苦労を知る人も増えます。」
と、農を軸に、まちのみんなが幸せになる構想を語ってくれました。
日本一ごみの少ないまちに変えたコミュニティ農園
こうした活動が実を結び、日野市では先頃、人口10万人以上50万人未満の市町村で、「1人1日当たりのごみ排出量」が600.5gと、全国一少ないまちになりました。
生ごみは宝だ!という市民の活動から始まったコミュニティガーデン。20年余りの時を経て、地域を宝と笑顔あふれるまちに変えていました。
せせらぎ農園に参加したい、遊びに行くには?
どなたでも参加できます。作業日は、火、木、日曜の週3回。
主要メンバー約30人が会員となり、年間12,000円の会費を払って運営しています。
単発で農作業だけする人は無料。
農作業に参加して、野菜を持ち帰る人は1回500円。
ただし、あくまでもコミュニティガーデンなので作業をせずに野菜だけを買うことはできません。
ベジアナの取材後記

生ごみを生かすという環境問題から始まったコミュニティガーデン。改めて、こうした市民活動を20年以上続けるというのは、並大抵のことではありません。
代表の佐藤さんは、長い活動の間には何人もの仲間を、高齢や病により見送ったと話してくださいました。それだけ地域の多様な人々の「居場所」であったということです。
せせらぎ農園という「コミュニティの場」は、土づくり、野菜づくりから、環境、教育、福祉の役割まで担い、住民自ら動いて、地域をよくする「市民パワー」発揮の場にもなっていました。これぞ三方よしであり、持続可能と呼ぶのでしょう。
隣近所の関係が希薄な都市におけるコミュニティガーデンの存在は、いまの消費生活に足りないものを「農」が提供しているようにも思えます。
菌も活躍し、人も活躍する!生ごみ堆肥のコミュニティガーデンの広がりは、都市農業や都市農家への理解にもつながると確信しました。

-
野菜を作るアナウンサー「ベジアナ」
小谷 あゆみ/KOTANI AYUMI
世田谷の農業体験農園で野菜をつくるアナウンサー「ベジアナ」としてつくる喜び、農の多様な価値を発信。生産と消費のフェアな関係をめざして取材・講演活動を行う。
介護番組司会17年の経験から、老いを前向きな熟練ととらえ、農を軸に誰もが自分らしさを発揮できる「1億農ライフ」を提唱。
農林水産省/世界農業遺産等専門家会議委員ほか
JA世田谷目黒 畑の力菜園部長
日本農業新聞ほかコラム連載中
ベジアナが行く!「東京×カラフル×農業」
-
VOL_1
東京都民1,395万人の「TOKYO GROWN」
-
VOL_02
東京に「みどり」を届ける植木生産者は、約500軒
-
VOL_03
東京農業の発信拠点がなぜ赤坂に⁉ 作ったのは1人の農家の熱
-
VOL_04
練馬の農チューバー!吉田農場 年中無休のロッカー直売!
-
VOL_05
足立区のツマモノ農業⁈ 横山農園
-
VOL_06
東京の郊外・国立市谷保に広がる田園風景
-
VOL_07
東京でいちばん空が広い田園地帯⁉ 多摩開墾をみんなで耕す
-
VOL_08
江戸から続く循環型農法! 落ち葉をはいて堆肥にする馬場農園
-
VOL_09
練馬に参加型の「みらいのはたけ」オープン! 土に触れ、育て
-
VOL_10
全国都市農業フェスティバル! 開催直前インタビュー!
-
VOL_11
生ごみを宝に!市民が活躍するコミュニティガーデン ~日野市
-
VOL_12
東京のガストロノミーツーリズム 東京の食の魅力発見の旅 伝統
-
VOL_13
居酒屋×農園のコラボ「世田谷枝豆プロジェクト」
-
VOL_14
土・自然・人とふれあう 世田谷区の「桜丘農業公園」