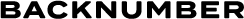花はおいしいのかまずいのか
「エディブルフラワー」とは文字通り「食べられる花」のこと。この「エディブルフラワー」という単語とともに、そのコンセプトがアメリカから日本に紹介されたのは1980年代でした。
あれから40年が経ち、エディブルフラワーはレストランの料理でもふつうに使われています。
また、スーパーでも売られるようになり、登場した頃のような目新しさは、個人的にはあまり感じなくなりました。

(料理に使用された花)八重咲のカリブラコア
それでは、日本の食のシーンにエディブルフラワーは定着したと言えるのでしょうか?
🔳 答えはNoです。
なぜなら、エディブルフラワーはまだまだ料理の飾りにすぎないから。食べてもらえずに残されているからです。食べられる花と名乗っておきながら食べられていないのでは、看板倒れもいいところ。レストランのシェフの肌感覚では、約8割の人がエディブルフラワーをお皿に残してしまっているそうです。
さて、埼玉県所沢市と新座市に挟まれた場所に位置する清瀬市は、耕地面積率が約17%と、全国平均の11.4%を上回り、東京都内でも上位に位置しています(耕地面積178 ha/総面積1,023 ha=17.4%)。※1
ちなみにニンジンの生産量は都内トップで、都全体の収穫量の3割以上を占めています(清瀬市で年間1,108 t、東京都全体の3割強)。※2
清瀬市の主業農家と準主業農家を合わせれば農家の数は100戸を超えます。ただ、そのほとんどが不動産経営所得を得ながら農業を営んでいます。それなりの事業規模で農業経営を続けている専業農家は、片手で足りる程度しか残っていません。※3
そのなかの一つ、横山園芸を訪問し、エディブルフラワーの最新事情を伺ってきました。
※1 出典:農林水産省『2020年農林業センサス』(市町村別統計表)
※2 出典:東京都農作物生産状況調査結果報告書(令和5年産)
※3 出典:農林水産省『2020年農林業センサス』
老いゆく父の体力不安対策で始めたエディブルフラワー
横山園芸は花農家として46年間経営を続けています。マイナーな花の生産と育種を行ってきたのが特徴で、クリスマスローズブームの火付け役そしてけん引役も果たしてきました。
2代目の横山直樹さんは25歳頃から、自社商品の宣伝と花好きを増やす目的で、メディアで花の魅力を伝え続けてきた人です。
父の代から改良を続けてきたクリスマスローズとダイヤモンドリリー(ネリネ)は、横山園芸の看板商品。コアな園芸ファンにとっては、横山園芸の花と横山直樹さんはごく身近な存在なのです。


(写真左)クリスマスローズ (写真右)ダイヤモンドリリー(ネリネ)
[写真提供:横山園芸]
オリジナル品種ばかりを生産してきた横山園芸は、競争にさらされることも少なく、堅実な経営を続けてきました。それにもかかわらず、突然エディブルフラワーに取り組み始めたのでした。
きっかけは、横山さんの父の体力不安でした。重量物を扱う鉢花生産には、体力勝負の一面があります。老いゆく父親に生産現場でいつまでも活躍してもらうには、軽いうえに移動距離が短くてすむ品目を、何か別に見つける必要があったのです。
エディブルフラワーを選んだのは、東京2020オリンピック・パラリンピック開催に向けて、知人から生産の話を持ちかけられたためでした。
挫折から成功までの紆余曲折
花の栽培には自信を持っていた横山さんでしたが、その自信は早々に打ち砕かれてしまいます。そして、じつに丸2年間、エディブルフラワーをまったく出荷できずに終わります。理由は、特定農薬がほとんどないエディブルフラワー栽培で、害虫や病気の発生を抑えられなかったからでした。
「同じ花なのに、口に入る食品に変わっただけで、何もかもうまくいかなくなるなんて想像できませんでした。」(横山さん)
その後、なんとか品質を高めることに成功し、顧客の評判も高まり軌道に乗ったところで、またしても想定外の出来事に見舞われてしまいます。2020年4月の新型コロナによる緊急事態宣言です。
エディブルフラワーは家庭消費がありません。ほとんどすべてが外食向け。横山園芸は再びまったく出荷できない状況に追い込まれてしまったのでした。
「まさに目の前が真っ暗になりましたよ。ようやく生産も販売も順調に回り始めたタイミングでしたから。」(横山さん)

悪いことは重なるもの。東京2020オリンピック・パラリンピックのビクトリーブーケの入札に際して、不当な利益を得ているとメディアに告発されてしまったのです。
「これには参りましたよ。メディアの完全な誤解で、犯罪者扱いで名前を晒されたんですから。情報化社会の怖さが身に沁みました。この時、そんなわけはないと火消しに走ってくれた仲間たちには、感謝してもしきれません。」(横山さん)
持ち前の粘り強さと明るさでこの危機を乗り越えた横山さんは、エディブルフラワーに付加価値をつけようと考え始めました。
「食べておいしい花を見つけることと、苦味やえぐみを減らす栽培方法との2つのアプローチでです。同じ品目でも品種によって味は違いますし、栽培方法の工夫でおいしくなったりもするんです。お腹がすかなくなるほど、何品種食べたかわからないくらい花を食べまくりました(笑)。」(横山さん)



東京産エディブルフラワーによる「新価値創造」
横山園芸にとってエディブルフラワー生産は、まさに新規事業。横山さん本人も従業員も、ここまでエディブルフラワーの生産量を増やすことになるとは、まったく想像していなかったそう。その原動力となったのが、生け花の資格をもっている横山さんだからこその唯一無二のパッケージでした。
「花屋さんのミニブーケを見て思いついちゃったんですよ。これだって。容器にただ詰められている花と、ブーケのようにかわいく束ねられているのと、どっちが魅力的かっていったら決まってますよね。」(横山さん)




出荷してお終いにせず自ら飾ることもしてきた横山さんだからこそ、新たな経済価値にも気づけたのでしょう。しかも見た目の美しさだけではありません。鮮度保持に加えて、たとえ輸送時に落とされても、まったく型崩れしないことまで計算つくされたパッケージなのです。
「こんなことはすぐに真似されそうな気がしたんですけど、真似されていません。手がかかるしオペレーションも大変。友人たちは皆、特許や実用新案を取れって言ってくれました。でも、エディブルフラワーのマーケットが拡大する方が重要だと考えてやりませんでした。」(横山さん)

(ミニブーケの花)マリーゴールド、ジャメスブリテニア、ストック、ペンタス、アンゲロニア
さらに目を引くのが、他では見られない珍しい花がたくさん入っていること。横山園芸のエディブルフラワーの種類は、品目にして20程度、品種数にすれば100を超えているのですから。ここまで多種多様な花を供給できる生産者は他にいません。
「これは後でわかったことですが、少量多品種生産のメリットなんです。色々な植物を少しずつ分散させてあちこちに配置することが、リスク分散になるだけでなく、害虫や病気の爆発的な発生を防いでもくれているんです。」(横山さん)

さて、エディブルフラワーを出荷できるようになって6年目の経営状況はどうなっているのでしょうか。
「おかげさまで売上の約半分がエディブルフラワーになりました。ここまで坪単価の高くできる品目は他にないと思います。東京という地の利も確かにあります。固定客がたくさんついてくださっていて、口コミだけでほぼ完売状態。正直、新規の注文に応えにくくなっています。」(横山さん)
横山園芸が描くエディブルフラワーの未来予想図
横山さんは優れた育種家でもあります。育種家としてのスキルや経験は、エディブルフラワー事業で何か役に立っているのでしょうか。
「う~ん、何もないような気がします。育種の経験が生きたというよりも、育種をやってきて知り合った仲間たちから、最新品種の苗を自分がほしい時にいつでも購入できる。この信頼関係がとても大きいです。だから、うちのエディブルフラワーは顧客に絶対に飽きられない自信があります。」(横山さん)

(料理に使用された花)ジャメスブリテニア
横山さんは、ある有名レストランのシェフからのひと言が、一生の宝物になったという。
「シェフと話をしていた時に、突然こんなことを言われたんです。『花は必需品だね』って。思わず聞き返しちゃいました。だって、このひと言を料理人から聞きたくって頑張ってきたんですから。エディブルフラワーなしでは料理が成立しない時代になったんです。うちの花の場合、約8割のお客さんが完食してくれているらしいです!」
「花にはそれぞれ個性的な味があります。進んでいるシェフは、すでにその花独特の味を生かした料理を提供し始めているんですよ。」(横山さん)
横山さんのエディブルフラワーを使いこなしているシェフたちは、使ったことがない色や形の花を見ると創作意欲が高まるのだそう。
「もう面白くてたまりません。自分自身、花の新たな一面に気づきますし、シェフたちとは知恵比べしているような感覚です。」(横山さん)

(料理に使用された花)マリーゴールドの花びら
最後に、横山さんにどう工夫してもおいしくならず、商品に加えられない花が何か尋ねてみました。
「バラとジニア(百日草)です。どっちもとても料理を引き立てるステキな花ですし、売りたくてたまりません。でも、まずいんですよ。食べておいしくない花は生産しない。これが僕のポリシーですから。」(横山さん)
幼い頃から花の力を信じ続けてきた横山さん。横山さんが描くエディブルフラワーの未来予想図は、誰もが花を五感で楽しむ世界でした。


-
品種ナビゲーター NPO法人スマート・テロワール協会顧問
竹下 大学/DAIGAKU TAKESHITA
東京都新宿区出身。千葉大学園芸学部卒業。
キリンビール入社後、ゼロから育種プログラムを立ち上げ、同社アグリバイオ事業随一の高収益ビジネスモデルを確立。国内外で130品種を商品化。
2004年には、All-America Selectionsが、北米の園芸産業発展に貢献した品種を育成した育種家に贈る「ブリーダーズカップ」の初代受賞者に、世界でただ一人選ばれた。
一般財団法人食品産業センター勤務を経て独立。
農作物・食文化・イノベーション・人材育成・健康の切り口から様々な情報発信やコンサルティングを行っている。
著書に『日本の果物はすごい』(中公新書)、『日本の品種はすごい』(中公新書)、『野菜と果物 すごい品種図鑑』(エクスナレッジ)など。
NPO法人テクノ未来塾理事
「本場の本物」審査専門委員
全国新品種育成者の会育種賞審査員
▶筆者HP:https://peraichi.com/landing_pages/view/takeshita/