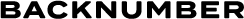世界に誇る食のまち、東京。
東京産の「農」と「食」の魅力を発信するイベント「東京味わいフェスタ 2022」が、10月28日から30日までの3日間、丸の内・有楽町・日比谷・豊洲の4エリアで開催されました。
4年ぶりの実施とあって、多くの人でにぎわい、丸の内会場行幸通りのステージには、東京産の野菜で作られた「東京やさい船」が飾られました。
高さ3mほどある東京産野菜の宝船の前でオープニングセレモニーが開かれ、小池百合子都知事が挨拶しました。
「ミシュランの数が世界で一番多い美食都市の東京は、有名なレストランやトップシェフと並んで、質の高い東京産の野菜をはじめ農産物が大きな魅力です。
イベントのシンボルとして、JA東京中央会の皆さまに東京野菜の宝船を作っていただきました。
東京農業の将来を担う3人の農業男子が勢ぞろいし、東京を代表するシェフが腕を振るう農と食のマリアージュです。
東京の最大の力は、消費者力、そして舌の肥えたお客さま力です。東京産の食材を使うことは、緑を守り、地産地消で脱炭素にもつながるサスティナブルな取り組みです。環境や緑を守る東京農業のおいしさを世界に発信していきたい」。

東京のトップシェフを代表して、三國清三シェフは、
「うちのレストランでも東京産の野菜、特に江戸東京野菜を使っています。とれたての野菜は香りや鮮度がすばらしい。
東京の農産物を使うことは、イタリアのスローフードにおけるゼロkm運動の考えとも重なり、環境にもよい」
と話しました。
JA東京中央会の城田恆良会長が、
「東京の農業の特徴の一つは多様性。宝船の野菜を見ても、これだけの野菜がほとんどすべて東京産でそろうことは誇らしい」
と話すと、小池都知事やシェフたちも一斉に宝船を振り返り、見入っていました。

東京農業の広報大使、農業男子の三鷹市の岡田啓太さん、立川市の金子倫康さん、練馬区の髙橋徹さんの3人。
東京産の野菜を食べることは、環境をより良くすることやフードロスの解消、地産地消や食育にもつながるので大いに食べてくださいとアピール。

※ 写真左から、髙橋徹さん・岡田啓太さん・金子倫康さん。
野菜の宝船は、この本番の日から逆算し、2か月以上前から種まきをして育ててきました。
前回の記事でも紹介した生産者のJA東京スマイル青壮年部部長の中代秀崇さんは、
「直前に激しい雨が降り、大根やカブに痛みが出ないか心配しましたが、無事に飾られてほっとしています。」
JA東京青壮年組織協議会・会長の洒井雅博さんは、
「これだけの野菜を集めてくるのは、結構大変だと思うんですけど、これも東京の文化です。
毎年、明治神宮に奉納していますが、こういうステージで多くの人に見てもらえるのは嬉しいですね。」

※ 写真左から、中代秀崇さん・洒井雅博さん。
カラフルな野菜の宝船ですが、近づいてよく見ると、白菜の芯の部分をきれいに面取りしたり、あえて半分にカットして断面の黄色を見せたり、随所に工夫が見られます。

この野菜の宝船、前々日(10月26日)の15時過ぎから、JA東京スマイル本部の駐車場で、ハクサイの面取りや、各種野菜のサイズ調整と丸の内会場への運搬用に箱詰め作業が行われました。
参加したのは、足立地区、葛飾地区、江戸川地区の生産者とJA東京スマイル職員の約30人が集まって、組合長の激の元、約3時間かけて準備が行われました。
使用する野菜は12種類。
ダイコン100本、聖護院ダイコン250本、カブ200束、小松菜40束、ワケネギ90束、キャベツ100玉、白菜100玉、ブロッコリー200個、ニンジン120本などです。






前日(10月27日)の朝9時からは、会場での組み上げ作業です。
前々日に準備した野菜が、次々に運ばれてきました。
作業は、JA東京スマイル青壮年部のリーダーの指示で、手際よく且つ慎重にバランスを見ながら組上げられていきました。
お昼頃には、ほぼ完成の状態になり、翌日のオープンに備えることができました。






野菜の宝船は江戸時代、野菜を扱う商人たちが、正月の初荷に野菜で宝船をつくり、お得意様に収めたのが始まりとされ、その後は、毎年11月23日の新嘗祭で、明治神宮に奉納されています。
「新嘗祭」の「新」は新穀(初穂)、「嘗」は御馳走の意味で、、「収穫を祝い感謝する」ことから、今では勤労感謝の日となったのです。

食べられる野菜でできた宝船とあって、その行方が気になるところですが、展示翌日(10月29日)の午後には解体され、都内のフードバンクやこども食堂へ提供されました。




-
農ジャーナリスト・ベジアナ
小谷 あゆみ/KOTANI AYUMI
世田谷の農業体験農園で野菜をつくるアナウンサー「ベジアナ」としてつくる喜び、農の多様な価値を発信。生産と消費のフェアな関係をめざして取材・講演活動
介護番組司会17年の経験から、老いを前向きな熟練ととらえ、農を軸に誰もが自分らしさを発揮できる「1億農ライフ」を提唱
農林水産省/世界農業遺産等専門家会議委員ほか
JA世田谷目黒 畑の力菜園部長
日本農業新聞ほかコラム連載中