テンペって何?
テンペとは、大豆の煮豆をテンペ菌で無塩発酵したインドネシアの伝統食品。納豆のようなネバリや匂いがなく、豆そのものの甘みや風味が生きているので、納豆嫌いの人にもオススメです。栄養価も高く、妊娠中の女性や高齢者には欠かせない血清アルブミン値や葉酸値の改善、食物繊維も豊富で便通改善にも効果があります。また、ポリアミンと呼ばれるアミノ酸の含有量はトップクラス。アンチエイジング効果が期待できる嬉しい食品です。




今回は東京都府中市で1949年に創業した納豆屋さん『登喜和食品』で、こだわりの納豆と注目食材・テンペについて伺ってきました!そこには尽きぬ味へのこだわりと、日本の農業と食生活を支えたいと願う情熱がありました。
テンペとは、大豆の煮豆をテンペ菌で無塩発酵したインドネシアの伝統食品。納豆のようなネバリや匂いがなく、豆そのものの甘みや風味が生きているので、納豆嫌いの人にもオススメです。栄養価も高く、妊娠中の女性や高齢者には欠かせない血清アルブミン値や葉酸値の改善、食物繊維も豊富で便通改善にも効果があります。また、ポリアミンと呼ばれるアミノ酸の含有量はトップクラス。アンチエイジング効果が期待できる嬉しい食品です。

登喜和食品では美味しさにこだわり、加熱せずにそのまま食べられる『生てんぺ』を独自の製法で開発!豆そのものの甘みが活きており、塩も砂糖も使っていないのに、おやつ代わりにもピッタリ!
また、レシピのレパートリーも豊富。天ぷらにしたり、肉の代わりに炒めたり、サラダに加えてもOK。ペーストにしてクリームチーズと蜂蜜を混ぜてパテにしたり、スムージーなどのスイーツにも応用可能!
日常食として取り入れたい、理想的な発酵食品です。

納豆は納豆菌が、テンペはテンペ菌が作り出す発酵食品。その工場内は他の菌が入り込まないように、厳重管理されています。まず白衣を着て帽子を被り、エアーでホコリを除去。さらに粘着ローラーで衣服の上からゴミを取り去り、アルコール消毒をした上でようやく工場内へ。
工場ではちょうど煮豆に納豆菌を吹き付ける作業中。豆の甘い良い香りがします。「食べてみてください」と勧められ、菌を吹き付けたばかりの煮豆を食べてみたところ、豆の甘みにビックリ!ほのかに納豆の香りがするのですが粘りはなく、これが納豆になっていくのかと考えると、発酵食品の神秘を感じました。



この煮豆はパックに充填され、発酵室で発酵後、冷蔵庫で熟成をし納豆へと変化。包装されて出荷されます。冷蔵庫から出てきた納豆を包装する作業場には、納豆の芳醇な香りが漂い、先ほどの発酵前の豆の甘い香りから納豆へと変化していく様子を体感できました。
登喜和食品では豆を包む素材にもこだわり、天然の松経木や国内でも珍しい稲ワラを使用しています。もともと納豆菌は稲ワラや枯れ草にくっついている微生物・枯草菌の一種。大豆・納豆菌・水だけが材料の納豆にとって、納豆菌の性格は品質を大きく変えるキーアイテム。登喜和食品では、古代米の稲ワラから生まれた納豆菌を使用。雑味がなく風味が良い、粘りの強い納豆を作り出しています。



登喜和食品は日本の農村・農家の助けになりたいという願いから、すべての製品に国産素材の、しかも特別栽培(減農薬).JAS有機大豆を主に使用しています。また、誰が・いつ・どこで作ったかが分かるトレーサビリティというシステムを導入しており、安心・安全な食品を食卓へ届ける努力を惜しみません。消費者や生産農家との信頼関係を大切に、自信とこだわりを持って納豆・テンペを作り出しているのです。
その製品は、『東京都地域特産品認証食品・イイシナ』(商品に込めた思いやこだわり、味や品質等を審査し、都が認証した食品)に登録されています!
▽『東京都地域特産品認証食品・イイシナ』の詳細についてはこちらから
https://tokyogrown.jp/e_mark/
http://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.jp/norin/syoku/e-mark/
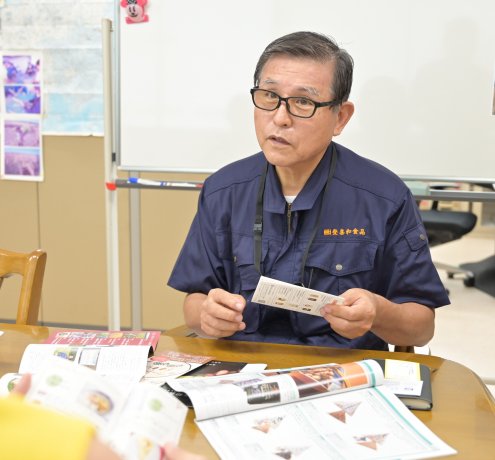


栄養価のあるものを美味しく消費者に届けたいという想いと、素材へのこだわりをとても強く感じました。初めて食べた『生てんぺ』は本当に豆の甘みや風味が濃く、毎日でも食べたい一品でした。どんどん世の中に普及していくことを期待しています。
▽株式会社 登喜和食品
納豆(遊作納豆・ひきわり納豆・多磨納豆・黒豆納豆)
/てんぺ(べっぴんテンペポタージュ・生てんぺ・黒生てんぺ)
https://tokyogrown.jp/e_mark/detail?id=571429
▽登喜和食品さんの直売所『大豆の里』
https://tokyogrown.jp/e_mark/shop/detail?id=572001
▽笹野美紀恵(TOKYOLOVERS NO_01)
https://tokyogrown.jp/tokyolovers/member/mikie_sasano/




