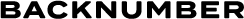東京産食材を使った料理を味わい、体験することで「食」や「農」の多彩な魅力を発見するイベント「東京味わいフェスタ2024(TASTE of TOKYO)」が、10月25日(金)から27日(日)の3日間、丸の内・有楽町・日比谷・豊洲の4会場にて開催されました。
レポート初回では、開催初日に行われたオープニングセレモニー(丸の内会場)と、オープニングトークショー(日比谷会場)の様子をお伝えします。
オープニングセレモニー(丸の内会場・行幸通りステージ)
東京駅の駅舎を一望する丸の内会場の行幸通りステージで、主催者の東京都、小池百合子知事の挨拶からオープニングセレモニーが始まりました。
「東京の新鮮な食材、農と食の両方の魅力を感じていただくために、丸の内、日比谷、有楽町、豊洲の4カ所での趣向を凝らした企画をご用意しました。
また海外でも注目されるのが日本の食文化で、インバウンドのお客様は東京のレストランのことも本当によくご存知です。食の魅力が東京の魅力に直接繋がっているなと思いますし、世界一の魅力都市・東京を堪能して欲しいと思います。
収穫の秋、食欲の秋。ぜひ、東京味わいフェスタを五感で楽しんでください!」

セレモニーには、東京の農林水産の第一線で活躍する方々も駆けつけ、コメントをいただきました。

「東京観光大使」三國 清三シェフ:東京の地産地消にこだわるナチュラルフレンチ「mikuni MARUNOUCHI」をプロデュース。「オテル・ドゥ・ミクニ」 オーナーシェフ
「東京には、地産地消がある。すぐそこにあります私のレストラン、mikuni MARUNOUCHIでは、味噌、醤油といった調味料から食材に至るまで、100%東京産を使っています。
東京には10,000件以上の農家の方がおられる。50品目ほどの伝統的な江戸東京野菜もある。どれも近くで生産されているので、風味よく、みずみずしい。私はその良さを、もっともっと広めていきたいと思っているので、ぜひこのイベントで体験して、宣伝してください!」

「東京観光大使」山下 春幸シェフ:伝統的スタイルと斬新な食材を組み合わせた“新和食”が人気の「HAL YAMASHITA」オーナー兼、エグゼクティブシェフ
「東京には、世界のトップシェフが集まっております。ビルや街のイメージが多いですが、島も、川も、山もある。
イベントでも多くの生産者の方の食材をシェフとのコラボで美味しい料理を出していきますので、この機会に東京産の素晴らしい食の魅力を、存分に楽しんで欲しいです。」

東京都農業協同組合中央会(JA東京中央会):野﨑 啓太郎 代表理事会長
「東京には約6,000ヘクタールの農地があり、一生懸命農家が生産しています。そして、何といっても消費地が一番近いのが魅力です。シェフの皆さんもお客さまにおいしい料理に提供してくださっているので、生産者としても、安全安心なうえ、新鮮でおいしい野菜を届けたいと思っております。
後ろには東京野菜で作った宝船がございます。JA東京むさしさんに作ってもらいましたが、こういうものも見ていただきながら、大いに東京野菜をPRしていきますので、よろしくお願いします。」



今年の「東京野菜宝船」の制作は、JA東京むさしが担当しました。開催日前日の午後2時過ぎから組上げ作業が始まりました。

「ミズとうきょう農業」の、梅村 桂さん(株式会社ネイバーズファーム代表取締役)
「日野市でトマト農家をしています。私も、東京で農業を始めてから、江戸時代やもっと昔から語り継がれ受け継がれる技術や文化がたくさんあることを感じます。
私の畑にはボランティアの方が来てくださるんですが、地域の方と一緒になって作れる農業も東京の農業の魅力だと思います。たくさんの人と一緒に農業を盛り上げていきたいです!」

「ミズとうきょう林業」の、 飯塚 潤子さん(株式会社東京チェンソーズ)
「今回は食のイベントと言う意味では、まず、山で食べる山弁は本当においしいです。空気もとてもおいしいです。東京には、ここから1時間半で山があります。実は東京の面積の4割が森林です。
林業は、森林から大きくなった木を収穫して、木材にしてきちんと利用できるように循環させている大事な産業です。インフラである水や空気を培う役割も、土砂災害を防止する面も担っています。私はそこに魅力を感じていますし、東京の森林のことを皆さんにもっと知ってほしいです!」

「ミスターとうきょう漁業」の、西田 圭志さん(三宅島漁業協同組合 組合員 西丸船主)
「東京の海には伊豆諸島、小笠原諸島を形成する複雑な地形があり、そこに黒潮が当たることにより、豊かな漁場が作られています。
そこで獲れた水産物を、鮮度の高いまま皆さんにお届けできるのが東京の漁場の魅力です!」
皆さんのさまざまな角度からのコメントで、期待が高まる「東京味わい味フェスタ」。
続いて、登壇者による東京産食材を使用した料理の試食に移りました。

使用した東京産食材を説明する、三國シェフ
三國シェフの考案した「東京ビーフ100%ハンバーグ」は、「東京根菜きんぴらと江戸甘味噌を使った照り焼きソースの雑穀ご飯丼ぶり」。
根菜きんぴらには、練馬区産のダイコン、青梅市産のニンジン、小平市産の滝野川ゴボウが使われています。ハンバーグの下には小平市産のコマツナ、清瀬市産のトマトが敷かれ、江戸甘味噌が添えられており、見事なまでに東京産食材が使用されています。

試食したハンバーグの美味しさに、笑顔がこぼれる小池都知事。
小池都知事:「一口いただきましたけど、もうおいしくて、おいしくて!しかも、食材全部が東京で採れるもの。フットプリント・環境負荷がとても低くて、その分新鮮。おいしくいただきました。」
セレモニーの最後に、味わいフェスタの成功を願って、八王子市産のパッションフルーツジュースで乾杯しました。使用したカップは環境負荷の少ないリユース品です。
東京産の農産物への期待が高まるオープニングセレモニーとなりました。

日比谷会場を彩る「TOKYO AJIWAI FESTA」
日比谷会場の入口でひと際目を引くのが、「TOKYO AJIWAI FESTA」と記された大きなモニュメントです。秋を感じさせる明るいオレンジ色の文字に、色鮮やかな植物が飾られたデザインが印象的で、通りがかった人々が思わず足を止めて写真を撮る光景が多く見られました。
さらに、会場では「Fermentation Tourism Tokyo ~発酵で旅する東京の森~」と題し、注目を集める発酵食品をテーマに、東京の食文化の豊かさを紹介するコンテンツが展開されています。




東京の発酵文化
江戸時代、すでに人口100万人を抱える大都市だった東京では、庶民文化の中で日本酒や味噌、醤油などの発酵食品が普及しました。
江戸時代から続く酒蔵は今も西部に多く存在し、調味料の生産拠点は都市化に伴い郊外や地方に移りました。
「TOKYO HAKKO TALK」で語られた東京の発酵文化

日比谷会場で開催されたトークイベント「TOKYO HAKKO TALK」では、「発酵デザイナー」という肩書きを持つ小倉ヒラク氏(発酵デパートメント)がメインスピーカーとして登壇しました。
ゲストには、醸造家の須合美智子氏(葡蔵人~BookRoad~)と、ゲストハウスやホステルの企画・運営に関わる石崎嵩人氏(BEER VISTA BREWERY)が参加し、それぞれの視点から発酵食品を通じた東京の食文化やトレンドについて語り合いました。
小倉ヒラク氏は、東京が豊かな自然環境と離島文化を背景に、多彩な発酵食品を生み出す都市であることを強調されていました。

Q:「東京の発酵」って何ですか?
小倉氏:東京は「消費の街」だけでなく、「ものづくりの街」でもあります。都の面積の約40%は森林で、緑豊かな都市なんです。奥多摩地域には水源があり、質の高い水が湧いています。東京のことを調べると、そのポテンシャルに驚かされます。
発酵食品も、伝統的なものからモダンなものまで多彩です。都内にはワインやビールの醸造所、味噌蔵、本格チーズを作る場所もあります。
また、新島や青ヶ島などの離島では「くさや」や「青酎」といった独自の発酵文化が根付いています。
東京には幅広くユニークな発酵文化があり、それが東京の“ヤバさ”です。
須合美智子氏は、都心でのワイン醸造を通じ、初心者でも気軽に楽しめる身近なワイン作りを目指していると語りました。

小倉氏:須合さん、東京でワインを醸造する思いは?
須合氏:ワインをもっと身近に感じてほしいんです。ぶどう畑は都市部では難しいけれど、醸造なら狭い場所でも可能です。
例えば、山梨のワイナリーは遠いため、訪問には事前の計画が必要ですが、都内の仲御徒町なら「この後行ってみよう」と気軽に立ち寄れます。それが、都内でのワイン醸造を始めた理由です。
ワイン好きだけでなく、初心者にも楽しんでもらいたい。親世代には重厚なイメージがあるワインを、もっと身近に。「どんなシーンで飲むか」をラベルのデザインで提案しています。
例えば、デラウェアのスパークリングには「公園に持っていこう」というヒントを込めました。春が待ち遠しくなるようなワインを目指しています。
石崎嵩人氏は、ホステルを拠点に「誰かと乾杯したくなる」クラフトビールを展開し、地域密着型醸造の魅力を紹介されました。

小倉氏:ホステルからビール醸造まで。幅広いですね、石崎さん!
石崎氏:僕らBackpackers’ Japanはゲストハウス運営から始まり、2021年にクラフトビール事業「BEER VISTA BREWERY」を始めました。宿のバーでスタッフがクラフトビールにハマったのがきっかけです。
飲む人が楽しめる「明るくて美味しいビール」を目指して、今では、年間30種類以上のビールを醸造しています。
僕らは、個性が立ったものというより、純粋に美味しくて、誰かと乾杯したくなる「明るいビール」を作っています。
東京では大量生産が難しい分、地域の人に喜んでもらえるビールを作ることに集中しています。
発酵食品を切り口に、東京の新たな魅力を発信したこのイベントは、多くの来場者の関心を集め、今後の展開に期待が高まりました。
取材後記
“地産地消”のありがたみを感じる丸の内会場でのセレモニーから、日比谷会場での“東京の発酵文化”のイベントと、まさに「東京味わいフェスタ」に相応しいオープニングでした。
次回は、有楽町会場で開催された、「江戸東京野菜『都内高校生・料理コンテスト2024』表彰式」と「第53回東京都農業祭」の模様をレポートします。

-
都市農業ライター
三文字 祥子/SHOKO SAMMONJI
都市農業ライター「畑と私」
広告などの企画・編集・コピーライターを続けてきた傍ら、練馬区での都市農業を楽しんで暮らす。
農業から自然や環境、収穫物を食卓に載せるまでの工夫を考えるのが好き。
趣味は三味線、民謡、盆踊り。