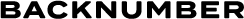渋谷駅から電車で1駅、池尻大橋駅から徒歩10分。
かつて中学校だった校舎の屋上に、2025年7月、新しい形の都市型コミュニティ農園「ART FARM IKEJIRI(アートファームイケジリ)」がオープンしました。
一般的な市民農園や貸農園のように個人の区画を借りて栽培するのではなく、「みんなで育てて、みんなで収穫する」スタイルが特徴。都心での“アーバンファーミング”のモデルとして、都市生活者と農の距離をぐっと近づけます。
都会の真ん中で広がる緑と人のつながり――その開園直後の様子を取材しました。
世田谷の緑の風を感じられる、元中学校屋上
伺ったのは7月下旬。うだるような暑さの中、駅から農園へ向かうと、いかにも校舎の風情が残る建物が現れます。
2025年4月、旧世田谷区立池尻中学校の跡地に、「次世代からの宿題をみんなで解決する」をコンセプトに掲げた複合施設「HOME/WORK VILLAGE」がリニューアルオープンしました。施設内には、シェアオフィスやレンタルオフィスのほか、レストランやビールの醸造所なども入居しています。
小中学校時代の記憶を呼び覚ます、光沢のある石製の階段を上がっていくと、「SHARE SEEDS」の黒板が目に入ります。ここは自家採取した種などを自由に持ち帰ることができるコーナーで、農園の入り口に設けられています。そして、かつて体育道具などが置かれていたのではないかと思われる踊り場から屋上へ抜けると、空が大きく広がり、涼やかな風が吹き抜けていました。

世田谷区立中学校の跡地を活用した多目的施設
ビニールハウスのフレームを活用した休憩スペースはウッドチップに囲まれ、栽培スペースには水田などで使う「あぜ板」を用いたレイズドベッド(地面より高く盛り上げられた花壇)方式の菜園が並びます。開園は7月下旬でしたが、作付けは5月頃から始めていたとのことで、バジルやエダマメ、スイカなどはすでに収穫できる状態になっていました。
菜園の横には、カフェのキッチンカウンターのようなスペースがあり、ここで簡単な調理も可能です。



稲やワイン用ブドウ、ホップなども栽培している。
「人と自然の共創から都市に循環と粋な文化を育てるルーフトップファーム」というコンセプトを掲げ、この農園を運営するのは「The Art Farm合同会社」。共同代表の一人である小野勝彦さんに、園内を案内していただきました。
「アーバンファーミング」の書籍が開園のノウハウに
「自分たちで農園を運営するなんて、最初は考えてもいなかったんです(笑)。『Urban Farming Life』という本を、さまざまな都市農園を取材しながら制作・出版したところ、ここ『HOME/WORK VILLAGE』を運営する方から『屋上農園を運営できる人を紹介してくれないか』と声をかけられまして。だったら自分たちでやってみようか、と踏み切ったのがきっかけでした」(小野さん)

共同代表の1人、小野勝彦さん。
もともとは、大手広告代理店の研究機関による循環型社会に関する研究として始まった「アーバンファーミング」への取り組みでした。「TOKYOを食べられる森にしよう」というスローガンのもと、都心部にある農園の事例や農的活動に取り組む方々を取材し、アーバンファーミングの6つの役割として整理。さらに、都心部の空き地を活用した農園づくりのノウハウもまとめました。
せっかく集めたこの情報を実践に落とし込み、アーバンファーミングのモデルケースを作ろう――それが今回の農園スタートにつながりました。
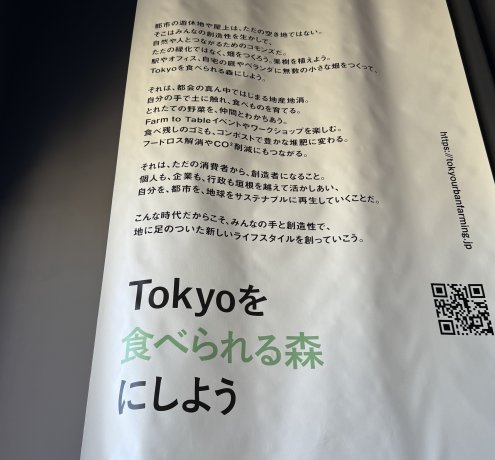

「屋上や空き地を利用した農園では、ビルオーナーによる付加価値創出や、行政との連携によって地代がかからないなど、運営コストを抑えている例も多いのですが、ここでは利用料をお支払いしながら、スタッフの人件費もまかなっていこうという取り組みです。勝算が十分にあったわけではないんですが、3人のスタートメンバーの勢いで始めてしまったところがあります(笑)」
勢いで始まったこのプロジェクトですが、賛同者や農園に関わるコミュニティメンバーを募ったクラウドファンディングでは、238人から約450万円を集めることに成功。月額3,000円の「クリエイティブメンバー」という会員制を基本に、屋上上映会やワークショップ、撮影利用などの空間活用を進め、収益化を目指していく予定です。

公共施設が「コミュニティ農園」として活用される未来
夕暮れどきになると、農園の会員の方々がちらほらと訪れ、水やりなどの手入れを始めます。台風予報が出ているこの日は、日よけシートが風で飛ばされないよう畳む作業も。日々の作業は、会員同士が手分けして進めています。
7月25日に開催されたオープニングイベントには、約100名が参加。月額会員も7月末時点で100名ほどとなり、この農園への期待の高さがうかがえます。

開園準備の作業にも、多くのメンバーが集まった。
この農園ならではの取り組みの一つが、養蜂スペースです。校舎の給水塔の柱をシートで囲み、その隙間からミツバチたちがせっせと出入りしていました。養蜂の管理は、屋上など都市養蜂に特化したチーム「Beeslow(ビースロー)」に委託しています。


給水塔を幕で覆った中に、蜂箱を設置。
「養蜂は農園の作物の受粉を助けるだけでなく、この地域にあるさまざまな植物の花から蜜を生み出してくれます。都市養蜂の魅力は、四季を通じて多種多様な花があること。そうした都市環境を参加者がより身近に感じられるように、農園の一角で日常的に観察でき、ハチミツも味わえる場にしていきたいと思います」(Beeslow代表・船山さん)

Beeslow代表の、船山 遥平さん。
作業が終わるころ、農園の栽培管理を取りまとめる共同代表の一人・石田紀佳さんから、とれたてのエダマメとカボチャをソーラークッカーでゆでたもの、そしてスイカが振る舞われました。




「都会で人と自然がつながるサードプレイスを目指しています。別に農作業をしなくても、ここに来るだけで気持ちがリセットされたり、仲間と会ってちょっとした会話が生まれたりして、また自分の場所に戻っていく。誰にとっても心地よい場所になるといいですね」(小野さん)

取材後記
少子高齢化が進み、いずれ東京でも人口減少が進むといわれています。
学校をはじめとする公共施設も形を変えていくことが必須となる中、農的な空間の創出は有望な利活用の一つでしょう。
都心の農的空間が事業として持続していく道のりは容易ではありませんが、それぞれのユニークな挑戦が、都市の“みどり”のあり方を新しく発展させていく可能性に期待せずにはいられません。

ART FARM IKEJIRI
HPはコチラから:https://www.artfarmikejiri.com/

-
㈱農天気 代表取締役 NPO法人くにたち農園の会 前理事長
小野 淳/ATUSHI ONO
1974年生まれ。神奈川県横須賀市出身。TV番組ディレクターとして環境問題番組「素敵な宇宙船地球号」などを制作。
30歳で農業に転職、農業生産法人にて有機JAS農業や流通、貸農園の運営などに携わったのち2014年(株)農天気設立。
東京国立市のコミュニティ農園「くにたち はたけんぼ」「子育て古民家つちのこや」「ゲストハウスここたまや」などを拠点に忍者体験・畑婚活・食農観光など幅広い農サービスを提供。
2020年にはNPO法人として認定こども園「国立富士見台団地 風の子」を開設。
NHK「菜園ライフ」監修・実演
著書に「都市農業必携ガイド」(農文協)「新・いまこそ農業」「東京農業クリエイターズ」「食と農のプチ起業」(イカロス出版)
『みどり戦略 TOKYO農業サロン』
-
VOL_01
やり手農家たちの「堆肥づくり勉強会」@くにたち はたけんぼ
-
VOL_02
“コンポストアドバイザー鴨志田純”が目指す「まちなか農業」
-
VOL_03
東京の西側、2つの有機農業
-
VOL_04
肥料でも農薬でもない新しい資材 「バイオスティミュラント」と
-
VOL_05
「多摩の酪農発祥の地」で、はぐくまれた有機農家たち。
-
VOL_06
馬と羊を飼い、穀物を育てる理想の有機農家をめざす
-
VOL_07
女性が主体となれる農業経営の仕組みづくり ( 株式会社となっ
-
VOL_08
落ち葉を重ねて数百年 『 武蔵野の黒ボク土』をコミュニティ
-
VOL_09
小松菜400連作! 「全量残さず出荷、それこそが一番のエコだ
-
VOL_10
目黒で農地を残すには? コミュニティの拠点として都市農地を守
-
VOL_11
ヤギのナチュラルチーズで新規就農! 東京の山地農業にも勝算
-
VOL_12
「まちのタネ屋さん」は進化する! 野村植産と東京西洋野菜研究
-
VOL_13
「ガストロノミー」が、東京農業の新たな一手となる!
-
VOL_14
調布の農家が作ったアプリが大注目! 全国3万7千の農家が使
-
VOL_15
「自然の近くで暮らす」ライフスタイルも魅力的に! 新規就農
-
VOL_16
本屋さんのマルシェが地域をつなぐ 畑を中心に循環型社会のモデ
-
VOL_17
都市農地の価値を多くの人に! 板橋区「THE HASUNE
-
VOL_18
「次世代からの宿題」に取り組む屋上農園 “ART FARM
-
VOL_19
地域交流のハブとなるコミュニティ農園 「わくわく都民農園小金