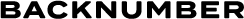自転車で少し走れば、農地が点在する東京都練馬区。
筆者(埼玉県狭山市出身)にとって、練馬区に住むまで農業は自分とは関係のないものだった。
それが、「練馬大根引っこ抜き大会」で初めて圃場に入ったのがきっかけで、数年前から区の農業体験農園を始めるに至り、徐々に都市農業に興味を持つように。
“農業素人”の筆者が感じる「農園・都市農業のある暮らし」をレポートします!
大会初参加では、圃場に入るのにも戸惑う。
15年前、結婚を機に練馬区に越してきた筆者が練馬駅で見つけたのは、「制限時間内に大根を抜く」という力自慢の大会(練馬大根引っこ抜き競技大会)の応募用紙。
早速、陸上部、バドミントン部、ソフトボール部、バレー部などの腕に覚えのある高校時代のメンツに声をかけた。
最初は農地に足を踏み入れるにも「え、靴、どうする?長靴?」と連絡を取り合い、筆者は初めて農業用のゴム長靴を買った。中には通勤に履くおしゃれ長靴で参加した仲間もいて、互いに「その長靴で走れるの?」と笑いあったものだ。
応援するだけだから、とスニーカーで圃場に入ってドロドロになってしまった友人もいて(大会が12月に開催されるので、年によっては霜柱が溶けてぬかるむことも。)、格好のチョイスで失敗するくらい、当時の私たちは農業と無縁だった。
しかし、この大会の楽しさで筆者はここから出場し続けることになる。
と言っても、当時は「農業に」というより、普段運動をしない筆者が「年に一度アスリートになれる」ことへの興味に惹かれていたのが正直なところだった。
コロナ禍で「都市型コンポスト」を経て、「農業体験農園」に。
急に一斉春休みが始まったコロナ禍初期、当時、小学校3年生だった息子が何を思ったか「生ゴミコンポストをやってみたい」と言い出し、そこから1年くらいは「マンションでも使えるコンポストで、ほとんど生ゴミが出ない暮らし」に楽しみを見出していた。
「微生物ってすごいね!!」なんて話しながら続けていたのだが、そのうちにどんどんできるコンポスト堆肥を「どこで使えばいいのか問題」にぶち当たり、農地でも借りたいね、と区に聞いてみると「農業体験農園(※)」なるものがあることを教わる。
(※)練馬区が発祥の制度。利用者は入園料・野菜収穫物代金を支払い、生産緑地を農園主から貸借する形で園主(農家)の指導のもと種まきや苗の植え付けから収穫まで、年間20種類以上もの収穫体験ができる。
▶ https://www.city.nerima.tokyo.jp/kankomoyoshi/nogyo/hureai/taikennoen.html

お借りしているのは、「イガさんの畑」。
園主は、五十嵐透さん。
▶ https://www.iga3farm.jp/wp/

道具も、肥料も、農薬も。必要なものが揃っているのでありがたい。使った道具は自分できれいに洗って戻す。
結論から言うと農業体験農園では指定の堆肥があることや、家庭で作るコンポストは塩気や油を含むので使えなかったのだが(そんなわけで今はコンポストはやめてしまった)、当時、外出や旅行の自粛が叫ばれ、子どもや自分の新しい体験として、息子もやる気だったのでとにかく始めてみよう、と応募したのだった(農業体験農園の利用は抽選で決まります)。
外でもマスクを強いられる空気感があった中、農地でマスクを外して過ごせることは、心が安らぐひとときで有り難かった。筆者と同じように、コロナ禍から農業に目を向ける家族も増えていた。
初めての農業は、知らないことばかり。
まず、子どもたちが喜んだのは「鍬で耕す」「広い土に種をまく」「ジョウロで水をまく」など、畑でのすべての行為。
マンション暮らしの我が家、ベランダでは土が風で飛んだり溢れるのがなんとなく億劫で、あまり積極的に土いじりをさせてあげていなかったのだと反省。
息子は普段見ることのない農機具にも興味津々で、特に農薬のポンプが好きでよく手伝ってくれた。
ちなみになんの自慢にもならないが、筆者は草花を育てるのがうまくはない。なので、種まきから収穫までの成功体験が最初にないと心が折れて続かない気がしたので、園主さんが農園のノウハウを教えてくれる農業体験農園はとてもありがたい施策と感じている。
農薬や種、それぞれのポイントは4年目の今でも完全に覚えられてないし、ものぐさな自分にとっては種まきなどのスケジュールが決められていることも心地よかったりする。

最初の作業は、自分の区画に沿って道を作る作業から。園主さんがトラクターで耕した畑はフカフカの土で、茶色い海のよう。

植える作物の場所も指定されているので、持ってきた肥料をどこに撒くかを間違わないように。「大根は白いから白いバケツ!」と念じながらいつも運んでくる。

一番“映える”枝豆の種(左)とインゲン豆の種(右)は、娘が楽しんで手伝ってくれる。枝豆は、絵本『そろいろのたね』のおうちの種みたいでかわいい。
春は、「ほうれん草」、「小松菜」。次に「キャベツ」、「大根」。
練馬区の農業体験農園では、毎年「30品もの野菜」を育てており、今(5月下旬)はちょうどほうれん草、小松菜を収穫し終え、これからキャベツや春大根の収穫が始めるところ(5月22日現在)。

春に植える野菜一覧。金・土・日のどこかで講習に来て、自分の区画で育てていく。初めて見たときは種類の多さに驚いた。あまり買わない野菜(枝豆やツルなしインゲン)が採れる嬉しさも。

数週間前に植えた夏野菜。トマト、ミニトマト、きゅうり、なす、ピーマン、ミニカボチャ、ごま、イタリアンパセリ。我が家の食卓を支えてくれる同志的な存在。昨年から苗の違いがわかるようになった。

まだ出始めの頃の小松菜。サラダでぱくぱく食べられる。筋っぽくなってくると子どもに人気がなくなるので、収穫の時期を注意深く見極める必要がある。
今年はキャベツが苗の段階から鳥の被害があった上、植えてからもなんだか生育が微妙な年だ(園主さんによると3月に夏日があったのが原因かも、とのこと。)。また大根が写真のようにレース模様になってしまうくらい、黒い虫(カブラハバチの幼虫)が大発生だった。
青虫や芋虫系は、初年度の最初は取り除くにも叫ぶことも多かった筆者だが、特にキャベツはその場で潰さないとキャベツの葉の根本の方に転がり落ちていくので、手で潰している。あまりにたくさん潰したので「閻魔様に問いただされるか?」と心配になるくらい。

レース状の大根の葉っぱ。葉を振るとビニールマルチにポトポト落ちるのでそれをプチュプチュ潰す。先日は1時間で、30〜50匹くらい潰した。

モンシロチョウの幼虫を潰す様子。
幼虫も生きるのに必死なので葉脈に沿ってピーン!と擬態したり、パラシュート隊のように糸を引いて離れようとする。幼虫にとっては命懸けのかくれんぼである。

どこにいるかお分かりいただけるだろうか。

正解はこの辺(赤色→の先)。
種まきの時期が終わり、最近の作業は「管理」。
先日は、春の最後の講習会があった。
この回は、伸びてくる夏野菜の枝やツルをどうやって「いい感じ」に収穫できるか、を学ぶ。「いい感じ」、というのは限られた養分や日光などを効率的に植物に送るため、いい茎を選び、整理するということ。



ツルの管理の仕方を説明するイガさん。図では理解できても実物を前にするとわからないことも多い。
利用者の皆さんが、真剣に覗き込んでいるのは……

ミニカボチャの根本。この中から「親ヅル」「子ヅル」「孫ヅル」を見分けて間引く。
「こんな太いツルを切っていいの?」と思うような親ヅルを切る。
必要なのは正確な理解と勇気。。

トマトやキュウリは、風や重さで倒れないように支柱に結ぶ。夏野菜の成長は早いので、週に1度は見に行く。

写真左側が「脇芽があるトマト」。写真右側は脇芽を摘んだもの。初年度はこれがよくわからなくて、トマトがジャングルのように。途中で園主さんに間引いていただいた。



左から、ジャガイモの花。キュウリの花。ナスの花。どれも美しい。
キュウリもナスも下の方で花が咲く(実ができる)と、「子どもができたから、そこに養分を送らなきゃ!」と思って(←思ってるわけではないが)、上への成長の優先順位が低くなってしまうらしい。
だから、どちらも一輪目はとってしまう。「キュウリ、ナス、ごめん。」
苗に「がんばれ」虫に「ごめん」の、春のレポートでした。
必要なことだから仕方ないが、虫を潰し、花や最初の実を詰み、自然に謝ることの多い筆者である。
このような作業の積み重ねで野菜は育ち、私たちの食卓に上るわけで、本当に心からいただきます、と感謝できるのも農業に触れる醍醐味だろう。
次はいよいよ灼熱の夏がやってくる。今回ご紹介した農作物たちがこれからどのように育っていくか、次回のレポートをお待ちください。

-
都市農業ライター
三文字 祥子/SHOKO SAMMONJI
都市農業ライター「畑と私」
広告などの企画・編集・コピーライターを続けてきた傍ら、練馬区での都市農業を楽しんで暮らす。
農業から自然や環境、収穫物を食卓に載せるまでの工夫を考えるのが好き。
趣味は三味線、民謡、盆踊り。