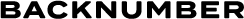煮豆を上手に作るのは、時間がある料理上手の人のすることと思っていました。
でも、実は思ったよりずっと手軽なんです。
今回は、豆の常備菜レシピと、食をめぐるグローバリゼーションのお話です。
基本の蒸し方
大豆は洗ってから、一晩以上(できれば一昼夜)しっかり浸水します。
大豆を戻した水を鍋に入れて、水が少なかったら足して、湯気の上がったせいろに入れて20分ほど蒸し、火を止めたらそのまま冷まします。
蒸すのではなく煮る場合も、弱火で20分ほどゆでてください。
大豆を戻した水は捨てるやり方もありますが、豆の出汁をより味わいたいので、私は戻した水を使っています。
豆は水につけるとおよそ2.5倍ほどに膨らみます。ゆで汁を使うと出汁と同様いたみやすく、保存期間は3~4日で食べきることを心掛けてください。
他の食品でも大豆を摂取しますから、一人あたり乾燥豆で50gくらいを作り置くとよいかもしれません。
イソフラボンの摂取については厚生労働省の「大豆及び大豆イソフラボンに関するQ&A」もご参照ください。

乾燥大豆100gを蒸しあげた状態。
指でつぶせる程度ではなく、ふっくら火が通った程度を目指します。せいろの直径は21㎝です。
蒸し豆をつかったレシピ
乾燥豆100gを戻してゆでた豆を活用する、そんなイメージのレシピをご紹介します。
具材の分量は、お好みに合わせて自由に調整して大丈夫です。
このほかにも、ひじき煮などの定番おかずも、自分で煮た豆を使うとさらに美味しく感じます。

豆のゆで汁を使えば出汁なしでもおいしく仕上がります。
【紫タマネギと大豆のマリネ】

大豆を蒸している間に、紫タマネギ(中1個程度)をみじん切りにします。
蒸しあがった大豆と合わせて、ひたひたになるくらいの白ワインビネガー(簡単酢などお好みのものでも構いません)とローリエ1枚(なくても大丈夫)を加え、漬けておきます。
筆者は、白ワインビネガーの代わりにホワイトバルサミコ酢を使うのが気に入っています。
このレシピは、豆のゆで汁が入らない分、比較的日持ちします。3日目あたりからタマネギの甘さが引き立ってさらに美味しくなります。5日程度で食べきるのがおすすめです。

みじん切りは、あまり細かくしすぎないほうが、シャリシャリとした食感が楽しめておいしいです。
このまま食べても、これからの季節にぴったりのさわやかな副菜になりますが、多めに作っておくとアレンジも自在です。
例えば以下のような料理も、時短でさっと仕上がります。
▪ツナ缶とマヨネーズで「ツナサラダ」
▪ひき肉と合わせて「チリコンカン」や「キーマカレー」
▪トマトスープに加えて「ミネストローネ」

「キーマカレー」への応用例です
【煎り酒の浸し豆】

作っておけば、さっとおつまみになる心強い味方です。
これからの季節にぴったりな、見た目にもさわやかな青大豆の浸し豆です。
基本の蒸し方と同じですが、12分程度の蒸し時間で少し固めに仕上げても美味しいです。
漬ける出汁は、白だしなどでもよいですが、筆者の最近のお気に入りは煎り酒です。
水またはゆで汁に、煎り酒を栄養成分表示の食塩相当量を参考に塩分濃度が0.5%から1%弱程度になるようなイメージで足します。
煎り酒は商品によって酸味と塩味のバランスが違うのでお好みのものを探していただくとよいのですが、塩分量が控えめのものの方がこのレシピにはよく合うようです。
おつまみとして出すときは、仕上げにラー油を垂らすと、喜ばれる方が多いです。

筆者がコロナ禍のリモートワーク中に日々食べていたフォー。
この写真ではお肉がありますが、お肉なしでも、あるいは汁なしの和え麺にラー油をかけるのもお勧めです。
レモンも香菜もトマトのマリネもカットして冷蔵庫に常備しているので、すぐに作れます。
ごはんにかけてさらさらと食べたり、茹でたエビや貝と和えたりと、浸し豆も活用の幅が広いです。
麺類のメニューにたんぱく質として添えると、栄養バランスも良いです。
【しもつかれ風の煮物】

栃木の旅館の朝食に出ていた「しもつかれ」に、何度も二日酔いを治してもらいました。
栃木の郷土料理「しもつかれ」からヒントを得た、素朴で味わい深いアレンジレシピです。
伝統的なしもつかれでは、鮭の頭や煎り大豆、酒粕、鬼おろしでおろした野菜を使いますが、今回は家庭で作りやすいように工夫しています。
ゆでた大豆は半量をフードプロセッサーで粗く刻み、残りはそのまま使います。
ダイコン(1/4本程度)とニンジン(1/2本程度)も同様に粗めに刻み、刻んだ油揚げ1枚、鮭の中骨缶(1缶)、酒粕大さじ2(またはお好みの量)を加え、ひたひたの出汁で軽く煮ます。
味を見て軽く塩を加え、魚醤又は薄口しょうゆをひと垂らしします。冷やして提供します。
お好みでオリーブオイルを回しかけると、洋風のニュアンスが加わって食べやすくなります。
食べ物と資本主義経済
今回のおすすめ書籍は、平賀緑著「食べものから学ぶ現代社会」(岩波ジュニア出版 2024年)です。
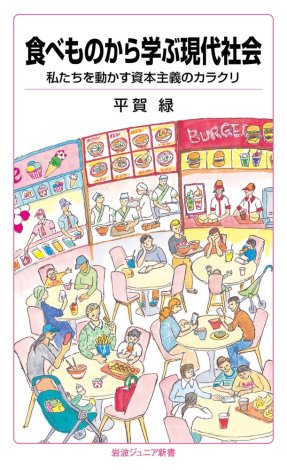
自分で畑を耕して食べることだけが目的であれば、売れるかどうかに関係なく食べたいものを育てるけれど、作物を売るとなれば同じものをたくさん作って効率的に儲けていかなければなりません。
そうした広がりが、国際貿易に進展し、金融市場と紐づいて、食品の国際貿易額は1990年代後半から倍増しました。
本書はこのような変化について分かりやすく紐解いている一冊です。
国際規模の食品企業は、多くの人が食品を摂取するための役割を果たしていますが、他方でより多くの自社商品を消費する食生活に消費者を誘惑し続けてもいます。
本書でも、ペリー来航前の食文化やラーメンが輸入小麦である「メリケン粉」から生まれた食文化であることなどに触れながら、世界中の多くの人が画一化された穀物等に依存し、食材の多様性が損なわれた結果、気候変動や病虫害、ウクライナ紛争やトランプ関税問題等で顕在化した国際情勢リスクにさらされてもいることも伝えています。
そして、それらの流れに抗う方法として、地域の農家や八百屋や食べる人たちがゆるくつながって、地域の共有の資産としての資源やコミュニティの価値を育てていく「コモンズとしての食」を提唱しています。
大豆を蒸す意味
大豆も、誰が作ったかに関係なく、市場で標準化され、先物取引の対象にもなっている「コモディティ商品」です。
国産の大豆は、外国産に比べて価格が高めに取引されていますが、豆腐のように消費者が値段に敏感な日常食品では、国産原料を好む消費者が多くても、結局は価格の安い外国産と競争しなければなりません。
実際、豆腐・納豆などの大豆加工品に使われている国産大豆の割合は、全体の約24%にとどまっています(出典:農林水産省 令和5年 食料需給表)。
また、地域の中で栽培されてきた伝統的な品種で種苗流通のための登録がされていない在来種といわれる品種は、国際食品市場の画一性の対極にある存在です。
収量は少なく病虫害にも強くありませんが、しっかりとした甘みや香り、地域ごとに異なる風味などの特徴を有しています。東京にも、青梅大豆、日の出大豆、鑾野(すずの)大豆、三河島大豆、東京八重生(やえなり)大豆など希少な在来種があります。
本書の著者である平賀氏は、まず自分でお茶を淹れることからお金の世界と距離をとることを実践してほしいと述べています。
現代社会の中でお金の世界との関係を手放すことはできることではありませんが、今回のレシピを通じて、皆さんにも外国産大豆を用いたプロテインなどの加工品を摂取する代わりに、国産大豆(手に入ればぜひ在来種)を調理していただいて、「コモンズとしての食」への思いを馳せていただきたいと願っています。

-
食農弁護士
桐谷 曜子/YOKO KIRITANI
1977年生まれ。神奈川県川崎市出身。大手法律事務所で弁護士として企業買収、企業法務に従事後、証券会社での勤務で地方創生、海外投資、ベンチャー投資等に深く関与。
その後、2014年から2022年まで農林中央金庫に在籍し、食産業及び農業に関する投資、国内外企業買収、各種リサーチや支援業務に携わる。
自他ともに認める食オタクであり、法務知識のみならず農林水産部門に関する知見を用いて、ベンチャー企業含む事業者や生産者の各種相談対応、新規事業創出支援、資金調達や事業承継支援を行う傍ら、料理で人を繋ぐことで課題解決への貢献を目指している。