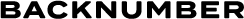《たかが1%、されど1%》
静かな夜。ベランダに出てみる。
手元にはあたたかな珈琲が湯気を立てている。
1,300万人もの人が暮らすという大東京の夜を見下ろして(と言ってみたものの、筆者のマンションは悲しいことに2階にある)、そこには1,300万のストーリーがあるということを考えてみたりする。
珈琲の、波打つ液面を見ていると、イメージははるか南米へ飛んでいく。
この珈琲がどこから来たものなのか、ブラジルなのかコロンビアなのか、でもそこにも自然と格闘しながら珈琲豆を生産する生産者がきっといて、でも、東京の片隅のベランダでその珈琲が飲まれていることは想像していないかもしれない、などと他愛のないことを考えたりもする。
この珈琲は、Amazonで気楽にクリックして買ったものだ(どうでもいいが、アマゾン川は南米にある)。
世界中から、なんでも手に入る。そういう世の中。
「僕たちの体は食べ物でできている、だから食べ物を大切にしないといけない。」
そういうお題目はよく聞くけど、ちょっと安易な気がしてもいる。
でも、間違いのない事実は、僕たちの体を物質としてみれば、世界中から来たものでそれは構成されているということだ。
では、この体のなかに、東京で生まれたものはどのくらい含まれているのだろう?
およそ、1%。
東京都の自給率だ。
ごくわずかな数字。
その1%を、東京のみなさんのもとに運ぶのが、東京産農産物の流通ベンチャーである僕たちの仕事だ。
では、1%に何の意味があるだろう。

僕なりの答えは、1%が分かれば、あとの99%は応用だ、ということだ。
東京という僕たちの足元には、若手からベテランまで、多様な農業生産者がいる。
思い立てば会いに行ける距離だから、けっこう、細かいこと(栽培の工夫とか)も伝えられる。生産している人の話を、それを食べる人に伝えることを「背景流通」と僕たちは呼んでいる。
僕たちが食べるものの1%について、その裏側にある生産者のストーリーや苦労がわかったならば、残りの99%――その半分が国産で、残りの半分が外国産――もイマジネーションで補えるように思う。
この珈琲の生産現場にもきっと深い背景があることだろう。
僕たちの体がいろんな食べ物でできている、という表現を借りるなら、むしろ、「僕たちの心はいろんな関係性でできている」。
そうであるならば、毎日の食卓に知っている人が作ったものが並ぶことは、なんというか、ちょっと特別な時間を僕たちにもたらしてくれると思っている。
ところで、東京の農業生産現場に行って、そしてその品物を運んでいて思うことは、この1%は侮れない、ということだ。
特別なことではない。
ただ単に、美味しい、のだ。

その美味しさは、生産地が近いがゆえの新鮮さと生産者の努力によるのだけど、それを伝えたくて仕方がない。ムズムズとする(そして、すぐにFacebookに投稿してしまう)。
僕たち流通業者のモチベーションの源泉もまた、特別なことはなにもない。すごくシンプルだ。
美味しいものを伝えたい。
その思いだけは、流通屋として、誰にも負けたくないと思っている。
でも、伝えていくには情熱だけではだめで、テクニックとかマネジメントとか、そういうことも大事になってきてしまう。それは畑の作物が思いだけでは美味しく育たないのと同じである。
ということで、畑にもストーリーがあるけど、それを運ぶ僕たちにも悪戦苦闘のストーリーがある。
ふつう、農業の主役は生産者であり、流通は黒子に徹するものだ。
しかし、今回、たった1%の、さらにそのごく一部を運ぶ僕たちにスポットライトをあてたコラムを書け、というお話をいただいた。
どうしたものかとも思ったが、流通の苦労話みたいなことも、もしかしたら、大都市東京の食卓のささやかな彩りになるかもしれないと考えて、しばらく書いてみたいと思います。
【株式会社エマリコくにたち創業者・菱沼勇介】

※今回のコラムシリーズは、地域内流通に焦点を当て、株式会社エマリコくにたちの皆様に執筆を依頼しました。

-
株式会社エマリコくにたち
代表取締役 菱沼勇介/HISHINUMA YUSUKE
株式会社エマリコくにたち
- 電話
- 042-505-7315
- 所在地
- 〒186-0004 東京都国立市中一丁目1番1号
- WEBサイト
- http://www.emalico.com/