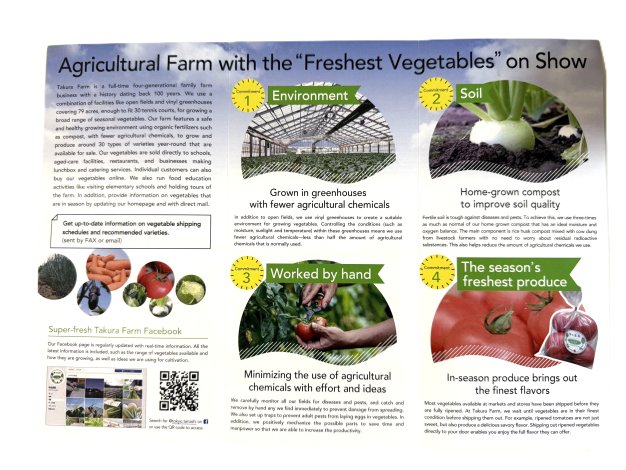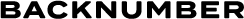東京の農業を未来に残すために、今できることを 「農業を続ける意味」を問い続ける日々
「東京の農業って、実はすごく危うい状態なんです。」と田倉さんは静かに語ります。
都市部の農業は、土地利用のコストや相続等の問題、周辺住民への配慮など、さまざまな課題に直面しています。また、農地の宅地化が進む中で、やむを得ず農業を続けない、あるいは続けられないという選択をする方も増えてきています。
「うちも数年前に相続があり、畑を手放すという選択肢も当然出てきました。でも、東京に農業がなくなる未来を考えると、それは違うと思ったんです。」
そのとき田倉さんは、保有していた不動産を売却して納税し、畑を守るという決断を下しました。
「正直、そんなことする人は少ないでしょうね。周りからは『なんで?』って言われます。でも、“今日、自分にできる最善の選択”を続けていくしかない。それが未来の農業につながると思っています。」