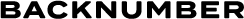「完熟」を、地元で食べてもらいたい
東京都清瀬市。緑豊かなこの街で「Tucciいちご農園」は2022年に誕生しました。
農園主の土屋圭緒理さんがこだわっているのは、地元で採れた新鮮ないちごを、その日のうちに味わってもらう「地産地消」のスタイル。配送は一切せず、完熟したイチゴを早朝に収穫し、その日のうちに直売所で販売しています。
「完熟したイチゴの味わいは格別です。お客さまには、ぜひ“摘みたて”の美味しさをその日のうちに味わってほしいんです。」と語る土屋さん。手間も時間もかかる方法ですが、そのこだわりが、多くのリピーターを生んでいます。
農園では現在、「よつぼし」「かおりの」「紅ほっぺ」の3品種を販売しています。その中でも最も人気なのが「よつぼし」です。
甘味、酸味、風味、美味がよつぼし級に優れているともいわれ、第3回全国いちご選手権で金賞を受賞した品種でもあることから、販売開始と同時にすぐに売り切れてしまうほどの人気を誇っています。