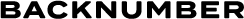写真上:自宅を改装した農家レストラン「PLANT」

東京をもっと魅力的にする農家同士の勉強会「みどり戦略TOKYO農業サロン」。
今回は板橋区で農家レストランも営む「THE HASUNE FARM」を訪ねました。
板橋区はかつて東京屈指の「米どころ」でした。しかし、関東大震災をきっかけとした工場地の移転や戦後の大型団地開発などが進み、2023年の段階で耕地面積は12ha、販売農家の数は41軒までと減少しています。
しかしその板橋区で、新たに東京農業の未来を切り開こうという農業者が生まれています。
「実験の場」としての農家レストラン「PLANT」
「レストランを作りたいというよりは、何か実験の場を作りたいという思いがありました。23区の中で畑と食べる場がこんな近くにあることで何が起きるのか?と」
そう語るのは冨永悠さん。 板橋区、蓮根地区にある「THE HASUNE FARM」の園主であり、パートナーである川口真由美さんと一緒にレストラン「PLANT」を2021年に開業しました。
川口さんは蓮根地区で江戸時代から続く農家の家に生まれ、冨永さんは会社員をしていましたが、2019年に農地を受け継いで農家となりました。

「THE HASUNE FARM」園主の冨永悠さん
「PLANT」は「THE HASUNE FARM」の季節野菜を使用しながら、実験的に普段はなかなか食材として使用しないものも扱っています。
例えば、冬場に摘心(茎の分けつを促すために生長点をカットする方法)したソラマメの芽をパウダーにして練りこんだパン。 その他、自家製のミツバチのハチミツを使ったドリンクや、レストランの隣で飼育しているニワトリ「ネラ」(オランダ原種の品種)や卵を使ったプリンなど。
コースは予約のみで、アラカルトメニューは予約なしで入れます。農園のツアーとランチセットとなったプログラムなども要望に応じて行っています。
そしてレストランで出た食品残渣も、併設の堆肥場で分解されまた畑に還っていきます。

自家製ハチミツとウコンのドリンクと菊芋のスープ


レストラン内の直売ブースに置かれている「ネラの平飼い卵」と、客席奥にある明るい厨房
地域の資源循環のプラットフォームとしての堆肥場
レストランの敷地内には鶏小屋があり、さらにコンクリートで10区画に区切った本格的な堆肥場があります。
「レストランで出た生ごみはもちろん、学校給食の生ごみも引き取っています。 畜産が行われている地域であれば家畜糞を使った堆肥が一般的ですが、なるべく身近で手に入る有機物を使って堆肥作りをしています。」
他にも、落ち葉、精米所から出る米ぬか、もみ殻など植物性のものを中心に水、窒素、炭素の分量をコントロールすることで発酵熱を60℃以上に上げて完熟させる方法で成分を明確にし、基本的にはこの堆肥だけで栽培することが可能です。
住宅に囲まれた地域でこのように本格的な堆肥場をつくっているところは珍しいですが、むしろ、住宅街であるからこそ循環を実感できるモデルを作りたいという思いが冨永さんにはあります。
堆肥場のすぐ横には鶏小屋があり、食を提供する場であるレストランも隣接する、循環型農園という都内では貴重な空間を形成しています。


レストラン横にある鶏小屋
「発酵の過程ではどうしてもニオイもでます。作業日には周辺の方々に声をかけるなどして何とかやっていますが、気は使いますね」(冨永さん)


鶏小屋の横にある堆肥場
都市農業においては農作業をすることでの音やニオイ、土ぼこりなどの周辺住民へ及ぼす影響が課題となることが多々あります。
住環境と農業を分離して互いに目に入らないようにした方が作業としては合理的でしょう。 しかし、都市に農地を残して農業を営むこと自体の価値を多くの人が感じ始めているのも事実であり、都市農業振興基本法もそのような理念のもとに2015年に制定されました。
農業がもたらす恩恵を、都市住民が実感できる場をつくることが都市農業の大きな役割ともいえるでしょう。
「都市農地の価値を多くの人に」よりオープンな農園運営
都営三田線蓮根駅から徒歩5分の農園には日々多くの人が訪れます。
農園に併設された作業場兼、直売所を訪れる人だけではなく、農作業をサポートする援農ボランティアや研修生、そして農業体験に取り組む世界的なNGOウーフ(WWOOF)にも参加しており、宿泊場所を提供する代わりにウーファーと呼ばれる会員が農作業に参加する仕組みも取り入れています。
また、販売についてもCSA(コミュニティーサポーテッドアグリカルチャー)に力をいれています。 地域支援型農業とも呼ばれるこの方法は、定期的な野菜セットの購入を年間契約し、参加者は指定された期日に畑へ野菜を受け取りに来ます。



「THE HASUNE FARM」の圃場の様子(写真左・中)と圃場入り口にある直売カウンターの販売メニュー(写真右)
「THE HASUNE FARM」ではそれに加えて、メンバー向けの収穫体験や生ごみの引き取り、交流会の開催なども行っています。
CSAメンバー募集のコメントには「通年の野菜定期便を通して、長期的な関係性を築き、都市農業の大切さを伝え、価値を共有する活動と捉えています。 一人でも多くの方にご賛同いただき、その輪が広がることで、将来的に少しでも多くの農地を残し持続可能な社会にしていきたいというのが我々の想いです。」 という理念が謳われています。
「自分で料理もするのですが、夕食のメニューを考えながら野菜を収穫して、その数時間後には食卓に並んでいるっていうのは農業の醍醐味だなって思います。 会社員時代にはなかった心の余裕であったり幸福感あります。」(冨永さん)
現在では練馬区や埼玉県にも農地を広げて、面積は1ヘクタールほどとなりました。農地の拡大はもとより、農地へより深く関わる参加者を増やし、さらに農業経営としても持続性の高い仕組みを考えたいといいます。
農家も農地も少なくなっている板橋区ですが、学校給食への一斉出荷、区内の子供食堂への野菜提供など農家同士の連携は進んでいます。
まちなかに残された農地が地域の拠点となって、多くの人たちを引き寄せ、単に食材としての農産物や風景としての農地ではなく、日々の暮らしの中で欠かせないものとして都市農業が必要とされていくモデルが生まれつつあるように感じました。

■THE HASUNE FARM
住所: 東京都板橋区蓮根2丁目5
営業時間: 毎週火・木・土曜日9:00~12:00不定休
アクセス:都営三田線蓮根駅から徒歩8分
東京板橋区にある有機栽培の畑。まちの資源で循環し、採れた野菜でまちの人を繋げる。
■PLANT
住所: 東京都板橋区蓮根1丁目14−22
予約制: 予約はネットから
https://www.tablecheck.com/shops/plant/reserve
アクセス:都営三田線蓮根駅から徒歩12分
農と食の実験の場
Food creative labo by THE HASUNE FARM is proposing agri-new-culture.

-
㈱農天気 代表取締役 NPO法人くにたち農園の会 前理事長
小野 淳/ONO ATUSHI
1974年生まれ。神奈川県横須賀市出身。TV番組ディレクターとして環境問題番組「素敵な宇宙船地球号」などを制作。
30歳で農業に転職、農業生産法人にて有機JAS農業や流通、貸農園の運営などに携わったのち2014年(株)農天気設立。
東京国立市のコミュニティ農園「くにたち はたけんぼ」「子育て古民家つちのこや」「ゲストハウスここたまや」などを拠点に忍者体験・畑婚活・食農観光など幅広い農サービスを提供。
2020年にはNPO法人として認定こども園「国立富士見台団地 風の子」を開設。
NHK「菜園ライフ」監修・実演
著書に「都市農業必携ガイド」(農文協)「新・いまこそ農業」「東京農業クリエイターズ」「食と農のプチ起業」(イカロス出版)
『みどり戦略 TOKYO農業サロン』
-
VOL_01
やり手農家たちの「堆肥づくり勉強会」@くにたち はたけんぼ
-
VOL_02
“コンポストアドバイザー鴨志田純”が目指す「まちなか農業」
-
VOL_03
東京の西側、2つの有機農業
-
VOL_04
肥料でも農薬でもない新しい資材 「バイオスティミュラント」と
-
VOL_05
「多摩の酪農発祥の地」で、はぐくまれた有機農家たち。
-
VOL_06
馬と羊を飼い、穀物を育てる理想の有機農家をめざす
-
VOL_07
女性が主体となれる農業経営の仕組みづくり ( 株式会社となっ
-
VOL_08
落ち葉を重ねて数百年 『 武蔵野の黒ボク土』をコミュニティ
-
VOL_09
小松菜400連作! 「全量残さず出荷、それこそが一番のエコだ
-
VOL_10
目黒で農地を残すには? コミュニティの拠点として都市農地を守
-
VOL_11
ヤギのナチュラルチーズで新規就農! 東京の山地農業にも勝算
-
VOL_12
「まちのタネ屋さん」は進化する! 野村植産と東京西洋野菜研究
-
VOL_13
「ガストロノミー」が、東京農業の新たな一手となる!
-
VOL_14
調布の農家が作ったアプリが大注目! 全国3万7千の農家が使
-
VOL_15
「自然の近くで暮らす」ライフスタイルも魅力的に! 新規就農
-
VOL_16
本屋さんのマルシェが地域をつなぐ 畑を中心に循環型社会のモデ
-
VOL_17
都市農地の価値を多くの人に! 板橋区「THE HASUNE
-
VOL_18
「次世代からの宿題」に取り組む屋上農園 “ART FARM
-
VOL_19
地域交流のハブとなるコミュニティ農園 「わくわく都民農園小金