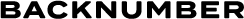こんにちは。管理栄養士・お野菜料理家として活動している、二児の母・今村結衣です。
「野菜は栄養のためだけじゃなくて、おいしくて楽しいからこそ、自然と食べたくなるもの」
そんな想いを大切にしながら、日々の暮らしに寄り添うレシピやコラムをお届けしています。
今回のテーマは、東京でできる“食育”。
過去のTOKYO GROWNの記事では、三鷹市の冨澤ファームを通じて、武蔵野台地で400年にわたって守られてきた「黒ボク土(くろぼくど)」と、その豊かな土が育む畑の魅力が紹介されました。
この土に育まれた伝統野菜「のらぼう菜」には、自然の力と代々続く農家さんの想いがぎゅっと詰まっています。
今回は、そののらぼう菜を使った『ごまツナ炒めのレシピ』をご紹介します。
家庭でも手軽に作れる一品で、土と野菜のつながりを“おいしく学ぶ”時間を楽しんでみませんか?
東京の畑を知ることが、食卓での会話のきっかけになる。
そんな“食育のはじまり”を、ぜひご家庭でも。
「土を育てる」冨澤ファームの物語と、今日できる小さな食育

冨澤ファームの園主である冨澤剛さんは、明治時代から続く農家の跡取り。かつて水も少なく、痩せた土地だった三鷹の地を、何世代にもわたって「土を育てる」ことで豊かな畑に変えてきました。
今では、近隣の大学や飲食店と連携しながら、落ち葉や馬ふん、生ごみを集めて地域のみんなで土づくりを続けています。
さらに、毎月第4土曜日には「畑のオープンキャンパス」を開催。地域の人たちと一緒に堆肥をつくり、畑に還す。そんな循環の体験の場にもなっています。
冨澤ファームさんの畑の土は、何百年の時と、人と人のつながりで育ってきた「みんなの土」なのです。
食育ポイント ①
▶︎ 食卓で「冨澤さんの野菜は、400年かけてみんなで育てた土から生まれてきたんだって!」と、食材や食材が育った環境について話す時間をつくることが大切です。
土も食べ物も人の手と時間で育まれていることを知り、食材にストーリーがあると、子どもも興味を持ちやすくなります。
▶︎ 買い物のときに「この野菜、どこで育ったんだろうね?」と話しかけてみるのもおすすめ。
特に地場野菜コーナーは地元で育った野菜がメインなので、親近感を持つキッカケにもなります。
黒ボク土ってどんな土?


畑の土を油圧ショベルで掘り起こすと、60~80㎝ほどで黒土から赤土に変わる。
黒ボク土(くろぼくど)は、火山灰と落ち葉などの有機物が混ざり合ってできた、栄養たっぷりの黒い土。
武蔵野台地では、何百年もかけてこの豊かな土壌を育ててきました。水はけがよくて、根菜や葉物野菜の栽培にぴったりな土です。

集められた生ごみは、畑で再発酵させる。
食育ポイント ②
▶︎ 「この土、どんな匂いがするかな?」「手ざわりは?」など、五感を使って感じてみよう。
土や自然にふれることで、“感じる力”を育みます。体感するにはぜひ冨澤ファームさんの畑のオープンキャンパスへ!
▶︎ 畑や土の写真や動画を見て、「土ってどうやって育つの?」と話し合ってみよう。
家にいながらでも、自然とのつながりを感じられます。
旬の葉物でパパッと!黒ボク土の恵みを味わうレシピ 【のらぼう菜のごまツナ炒め】

そんな“みんなで育てた黒ボク土”で元気に育ったのが、今が旬の「のらぼう菜」。
江戸時代から栽培されてきた東京の伝統野菜(江戸東京野菜)で、噛むほどに甘みがあり、アクが少なく、子どもにも食べやすい葉物野菜です。
今回ご紹介するのは、そんなのらぼう菜を使った簡単レシピ。
忙しい日でもパパッと作れて、たっぷりののらぼう菜をペロッと食べられる一品です!

材料(2人分)
● のらぼう菜…200g
● ツナ缶…1缶(80g)
● すりごま…大さじ1
● 醤油…大さじ1/2
● みりん…大さじ1/2
● 塩・こしょう…適量
● 油…大さじ1/2
作り方
1. のらぼう菜はよく洗い、食べやすい大きさに切る。下半分の茎と上半分の葉で分けておく。

2. フライパンにのらぼう菜の茎部分と油、水大さじ2(分量外)、塩ひとつまみを入れる。全体を菜箸でサッと混ぜ、フタをして中火にかける。

3. ジューっと音が立ってきたらそのまま3分蒸し焼きにする。茎部分に火が通ったら、葉部分を加えて塩をひとつまみ振り、炒める。

4. 色が鮮やかになるまで炒めたら、すりごまと汁気を切ったツナ、醤油、みりんを加える。すりごまとツナに調味料を吸わせるように全体を炒め合わせる。
最後に塩こしょうで味を整えて出来上がり!

調理のワンポイント!
油と水を使って蒸らし炒めにすることで、ぐっと甘みが引き立ちます。
太めの茎の場合は、固さを見ながら加熱時間を調整してみてくださいね。
適度にシャキシャキ感を残すと、野菜の元気さが伝わってきますよ。
食育ポイント ③
▶︎ 「のらぼう菜、どんなにおい?どんな食感?」と一緒に観察&試食してみよう。
素材の特徴に注目することで、味覚や感性を育てます。小松菜やほうれん草との食べ比べもおすすめです。
食べることは、土とつながること。今日からできる一歩

食べ物の背景には、人々の手間や工夫、何百年もの時間と、想いがつまっています。
冨澤ファームの「黒ボク土」は、まさにその結晶のような存在です。
食卓で「この野菜、どこから来たのかな?」「誰が育てたのかな?」「どんな土で育ったのかな?」そんな問いかけひとつで、食べる時間が、ただの栄養補給ではなく、心も体もあたたまる時間に変わります。
今日のごはんの時間がもっと豊かに、もっとあたたかくなりますように。

-
管理栄養士
今村 結衣/IMAMURA YUI
1995年生まれ。埼玉県出身。二児の母。女子栄養大学 栄養学部 実践栄養学科卒業後、青果物の専門商社でカット野菜工場の品質管理業務に従事。
その後、地域密着型の青果店で野菜の仕入れ、配送、営業等に携わる。その傍ら、野菜の切り方教室を開催。
結婚、出産を経て、野菜や農業に関わる企業のサポートやレシピ記事執筆を行っている。
Instagram▶https://www.instagram.com/ponsan.68/
東京の恵みdeおうち食育
-
VOL_01
「甘味」は食材から引き出す!
-
VOL_02
伝統の発酵調味料で東京の「塩味」を再発見!
-
VOL_03
東京食材で、おいしい「うま味」体験!
-
VOL_04
東京産の米酢に甘酒 発酵食品で「酸味」を学ぼう!
-
VOL_05
東京野菜でおいしく「苦味」を体験してみよう!
-
VOL_06
切って楽しむ東京野菜シリーズ「小松菜」
-
VOL_07
切って楽しむ東京野菜シリーズ 「キュウリ」と「ズッキーニ」
-
VOL_08
切って楽しむ東京野菜シリーズ 「トマト」
-
VOL_09
切って楽しむ東京野菜シリーズ「ピーマン」
-
VOL_10
切って楽しむ東京野菜シリーズ「サトイモ」
-
VOL_11
切って楽しむ東京野菜シリーズ「 カラフル大根&カブ」
-
VOL_12
切って楽しむ東京野菜シリーズ「 キャベツ」
-
VOL_13
切って楽しむ東京野菜シリーズ「カラフル人参」
-
VOL_14
色で楽しむ東京野菜シリーズ ~基本編~
-
VOL_15
色で楽しむ東京野菜シリーズ ~「きみどり」編~
-
VOL_16
色で楽しむ東京野菜シリーズ ~『あか』編~
-
VOL_17
色で楽しむ東京野菜シリーズ ~『橙色』編~
-
VOL_18
色で楽しむ東京野菜シリーズ ~『きいろ』編~
-
VOL_19
色で楽しむ東京野菜シリーズ ~『みどり』編~
-
VOL_20
三鷹市冨澤ファームの「黒ボク土」と、「のらぼう菜」のごまツナ
-
VOL_21
東京の農家と学ぶ!子どもと楽しむ「トマトの食育」 〜ネイバー
-
VOL_22
子どもと東京農業を学ぶ! ~繁昌農園の夏野菜で作るカレー風味
-
VOL_23
親子で東京農業を学ぶ! ~檜原村の生芋コンニャクで作るコク
-
VOL_24
親子で東京農業を学ぶ! ~三鷹市・吉野果樹園のリリコイバタ